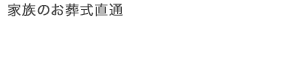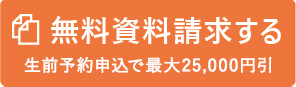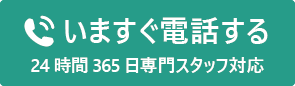葬儀・葬式に関するさまざまな用語をご紹介します
か行
- 開眼供養 (かいげんくよう)
- 仏壇を初めて購入した場合には、新しく本尊をお迎えするために僧侶を招き、開眼供養をします。眼を描き入れ仏に魂を迎え入れる儀式のこと。
- 改葬 (かいそう)
- 一度納めた遺骨を他の場所に移すことをいいます。改葬には書類上の手続きが必要で、まず現在の墓の管理をしている寺院および、移転先の寺院・霊園にあらかじめ、許可を取ります。旧墓地の管理者発行の埋蔵証明書、移転先の墓地発行の受け入れ証明書を添えて、それを旧墓地のある市区町村の戸籍課に提出し、改葬許可証を発行して貰うようにします。
- 戒名 (かいみょう)
- 戒を授けられ仏弟子となった者に授けられる名前のこと。日蓮宗では「法号」、真宗系では「法名」、天台宗、真言宗などでは「戒名」といわれます。
- 火葬 (かそう)
- 死体を焼き、残った骨を葬ることをいいます。明治時代に公衆衛生上の理由から政府が促進し、一般的に行われるようになりました。
- 形見分け (かたみわけ)
- 故人が生前に愛用していたものや思い出のものなどの一部を、近親者や親しい友人にわけて、形見の品物を通して故人を忘れることなく、偲ぶよすがにしてもらうことをいいます。
- 月忌 (がっき)
- 毎月の故人の命日にあたる日のことをいいます。
- 合掌 (がっしょう)
- 両方の手を合わせて礼拝することをいいます。神仏に祈ったり、死者に冥福を祈ったりするときの基本的な動作になります。
- カトリック
- キリスト教の一派のこと。カトリックはギリシャ語で「普遍的」という意味になります。
- 神棚封じ (かみだなふうじ)
- 死者を出した家の神棚を閉め、合わせ目に白い紙を張り、死忌が及ばないようにする措置のこと。四十九日あるいは五十日祭を終えて白紙を外します。
- 仮通夜 (かりつや)
- 日取りの関係、近親者が遠方など、時間がかかる場合に「通夜」を2日間にわたって行うことをいいます。1日目を「仮通夜」と呼び、家族や近親者で死者を見守ります。
- 棺掛け (かんかけ)
- 棺を覆う布のこと。神式では白布で覆います。
- 還骨法要 (かんこつほうよう)
- 火葬した遺骨を持ち帰って行うお勤めのこと。お骨になって帰ってきた故人を追悼する儀礼です。
- 灌頂 (かんちょう)
- 頭頂に水を注ぐこと。または、墓石に水をかけることをいいます。
- 忌明け法要 (きあけほうよう)
- 四十九日目の忌明け (満中陰)に行う法要のこと。
- 帰依 (きえ)
- 仏を信じ、その教えに従うことをいい、仏にすべてを捧げること。
- 北枕 (きたまくら)
- 死者を安置する際に、北に頭を向けること。この由来は、釈尊が入滅する時に頭を北向きにし、額を西の方に向き、右脇を下に寝ていた故事にならったものとされており、北枕が困難な場合には西枕にします。
- 忌中札 (きちゅうふだ)
- 喪家の入口に「忌中」と書いて貼る札のこと。
- 忌服 (きふく)
- 死者の遺族が、一定の期間喪に服するならわしのこと。
- キャスケット
- 日本でいう「棺」のことをいいます。「宝石の小箱」「貴重品入れ」から転じた言葉で、土葬用の装飾された棺のこと。
- 供花 (きょうか)
- 葬儀の際、お悔やみの気持ちを込めて送る生花のことをいいます。仏前や死者の前に花を供えること。
- 経帷子 (きょうかたびら)
- 死者を葬るとき、死者に着せる経の書かれた白い着物のことをいいます。
- 経机 (きょうづくえ)
- 経典を置いたり、読誦の時に用いる机のこと。
- 経典 (きょうてん)
- 仏教の教えを書いた書物のこといい、一般の檀家では、属している宗派の経本を用意します。
- 曲録 (きょくろく)
- 僧が法事のときに用いる椅子の一種。
- 清め塩 (きよめじお)
- 火葬場から帰宅した際、玄関先で手を洗い身体に塩をふりかけて清める習慣のこと。
- 釘打ち (くぎうち)
- 出棺に際して柩の蓋をし、遺族が小石を使って、棺の釘を打つ儀式のこと。死者が三途の川を無事に渡れるように願って打つものです。
- 繰り出し位牌 (くりだしいはい)
- 一つの位牌に何枚もの位牌札を、命日順に揃えて収容したもの。
- 袈裟 (けさ)
- 僧侶の衣服のこと。左方から右脇下にかけて衣をおおう、長方形の布。
- 結界 (けっかい)
- 一定の場所を区切って、そこを聖域とし、外側から不浄なものが入らないようにすること。葬儀においては、幕などで結界をつくります。
- 血脈 (けちみゃく)
- 教理や戒律が、師から弟子に授け伝える法統のことで、血のつながりにたとえた言葉。
- 献花 (けんか)
- 告別式のときに、死者に生花を捧げることをいいます。焼香の代わりに行うことが多いです。
- 献香 (けんこう)
- 霊前に香を焚いて神仏に捧げること。
- 献灯 (けんとう)
- 葬儀の開式時などにローソクに火を点ずることをいい、火は古来から不浄を焼き払うと言わます。
- 香典・香奠 (こうでん)
- 葬儀の際、霊前に香に代えて故人に供える金銭や物品のことをいいます。香典は社会通念上、課税対象にはなりません。
- 香典返し (こうでんがえし)
- 香典をいただいた方に、挨拶状を添えてお返しすること。
- 香炉 (こうろ)
- 香を焚くための器具のこと。
- 五具足 (ごぐそく)
- 仏前供養のため香炉を中心にその両横に燭台を置き、その両外側に花立てを配したもので、「五物具足」の略。
- 居士 (こじ)
- 在家の男子であって、仏教に帰依した者。または出家をせずに家庭において修行を行う仏教の信者のこと。男の戒名の下につける称で今日では浄土真宗以外の諸派で、戒名に用いています。
- 骨上げ (こつあげ)
- 火葬のあと、遺骨を箸で拾い骨壷に納めること。
- 骨壷 (こつつぼ)
- 火葬したお骨を収納するための壷のこと。